「釜石鉱山」について
釜石鉱山の歴史
釜石鉱山の歴史
History
江戸時代から始まり、明治・大正・昭和と日本の製鉄の発展とともに歩んできた釜石鉱山。
良質な鉄鉱石を産出する釜石鉱山は、「鉄の町」釜石を、そして日本の製鉄を百年以上に亘り支えてまいりました。
1857年(安政4年)
鉄鉱石に恵まれた甲子(かっし)村(むら)大橋(現在の釜石市大橋地区)に南部藩士大島(おおしま)高任(たかとう)によって、洋式高炉が作られ、日本で初めて鉄鉱石製錬に成功。我が国の近代製鉄の発祥とともに本格的な鉱山開発が始まる。

事務所前記念碑

近代製鉄の父・ 大島高任
1874年(明治7年)
明治政府により官営製鉄所となる。(後、明治16年に官営製鉄所閉鎖)
1876年(明治9年)
鉱山と釜石市を結ぶため、日本で3番目となる鉄道、釜石鉄道が起工される。
1885年(明治18年)
実業家、田中長兵衛が民営企業として再興に着手。
娘婿の横山久太郎と共に苦難の末、明治19年出銑(しゅせん)に成功。
同20年釜石鉱山田中製鉄所を創立。
1924年(大正13年)
三井鉱山株式会社の資本となり、釜石鉱山株式会社となる。
1934年(昭和9年)
戦時体制下で製鉄合同により釜石鉱山(株)、官営八幡製鉄所、輪西製鉄(株)、三菱製鉄(株)、富士製鋼(株)、九州製鋼(株)が合同し日本製鐵(株)が発足、釜石製鐵所となる。
鉱山は分離され、三井鉱山(株)の資本下の釜石鉱山(株)釜石鉱業所大橋採鉱所となる。
1939年(昭和14年)
日本製鐵(株)より分離独立して日鉄鉱業(株)が創立。
同年5月、日鉄鉱業(株)釜石鉱業所となる。
1950年(昭和25年)
新山坑で銅鉱床を発見。

S24頃 坑内採掘風景
1952年(昭和27年)
銅の選鉱場も作られ、鉄・銅併産体制が確立する。
※最盛期には3000人近くの人々が働いていました。

S20年代大橋社宅
1979年(昭和54年)
釜石鉱業所が日鉄鉱業(株)100%出資の釜石鉱山(株)に引き継がれる。
1988年(昭和63年)
事業転換を目的に、鉄・銅の残鉱整理と新規事業創出の新体制へ移行。
動燃原位置試験の受託事業開始。
1989年(平成1年)
鉱泉水(仙人秘水)の製造を開始する。
1992年(平成4年)
銅の採掘を終了する。
1993年(平成5年)
大規模な鉄鉱石の採掘を終了する。
新鉱山・鉱泉水・地下空洞跡地利用の事業を展開する。
※現在でも年間約100トンの生産販売を行なっています。
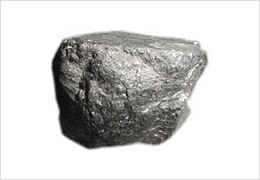
鉄鉱石
1997年(平成9年)
動燃原位置試験が終了する。
2001年(平成13年)
白色石灰石採掘事業から撤退。

坑内のご案内
坑内を利用した施設をご紹介